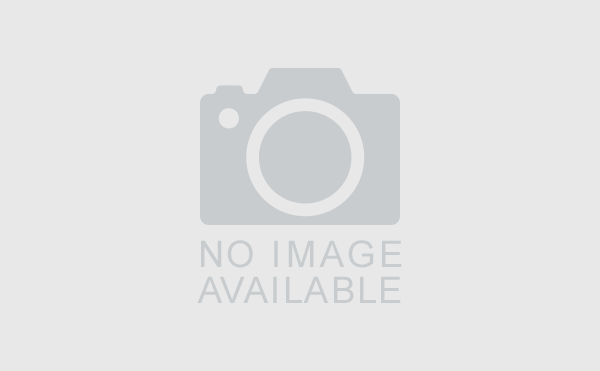墓じまいするのは大変?今と昔について
墓じまいするのは大変?今と昔について
「そろそろ墓じまいを考えなきゃいけないかもね」
最近、こんな言葉を親戚の集まりやお盆の時期に耳にすることが増えてきました。
けれど、「墓じまいって何?」「そんなに大変なの?」という疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
昔は「お墓を守ること」が家族や子孫の大切な役割でした。でも、今は時代が変わり、家族の形や暮らし方も多様になりました。それにともなって、お墓に対する考え方も変わりつつあります。今回は、「墓じまい」という言葉の意味と、昔と今でどう変わってきたのかを、やさしく、わかりやすくお話ししていきます。
■ そもそも「墓じまい」って何?
「墓じまい」とは、今あるお墓を撤去し、お墓の中にあるご遺骨を他の場所に移すことを言います。たとえば、地方にある先祖代々のお墓を撤去して、都会の納骨堂や樹木葬などに移すケースが増えています。
墓じまいの主な理由は以下のようなものです:
- お墓のある場所が遠くて、なかなかお参りに行けない
- 継ぐ人がいない、または子どもに負担をかけたくない
- 自分たちの代でお墓を終わらせたい
- 管理費を払うのが負担になってきた
昔はこういった理由でお墓をなくす、という考えは少なかったですが、今では決して珍しいことではありません。
■ 昔のお墓事情:守るのが「当たり前」
昔は、家制度や「本家・分家」といった考え方が根強く、「お墓は代々引き継ぐもの」とされていました。特に地方では、長男が家を継ぎ、仏壇やお墓もそのまま受け継ぐのが一般的。お盆やお彼岸には親戚が集まり、先祖を供養するのが年中行事でした。
また、お墓を守るということは、「家族を大事にする」「地域社会に根付いて生きている」という証でもありました。村の人同士で助け合い、お墓の掃除や供花も自然と役割分担されていた時代です。
今と比べて、家族のつながりも強く、地域の中で暮らしが完結していた時代だったからこそ、お墓を守ることも自然なことだったのです。
■ 現代のお墓事情:多様化と孤立化
ところが現代はどうでしょうか。都市部への人口集中、核家族化、そして少子高齢化など、社会の構造が大きく変わってきました。
たとえば、長男も東京、大阪といった都市部に就職し、親の家やお墓のある地元には年に一度しか帰らない。そうなると、先祖代々のお墓の世話がだんだんと難しくなってきます。
さらに、子どもがいない、あるいはいても「お墓の管理を任せるのは申し訳ない」という親世代も増えています。こうした背景から、「墓じまい」を前向きな選択ととらえる人も多くなっています。
最近では、納骨堂や永代供養、樹木葬、海洋散骨など、「お墓にとらわれない供養の形」が増えてきました。どれも「後に残された人が困らないように」という気持ちから選ばれているのが特徴です。
■ 墓じまいは大変?実際の手続きと心の問題
実際に墓じまいをするには、いくつかの手続きが必要になります。
- 遺骨の移動先(改葬先)を決める
- 役所に「改葬許可申請書」を提出する
- 墓石の撤去・処分を専門業者に依頼する
- お寺や霊園との相談・離檀料の支払いが発生することも
手続き自体は時間とお金がかかりますが、それ以上に大変なのは「心の整理」です。
「先祖に申し訳ない気がする」「親戚から反対されるかもしれない」など、精神的な負担が大きく、なかなか踏み切れない方もいます。
また、親戚の中にお墓に強い思い入れのある人がいた場合、話し合いが難航することもあります。墓じまいは「個人の決断」というより「家族全体の調整」が必要になる場面も多いのです。
■ 墓じまいは「終わり」ではなく「新しい形」
でも、忘れてはいけないのは、墓じまいは「ご先祖との縁を切ること」ではない、ということです。
むしろ、「今の時代に合った供養の形を考える」という、前向きな選択肢のひとつです。
現代では、自分のライフスタイルや家族の状況に合わせて、供養の形を自由に選べるようになってきています。
たとえば、デジタルお墓参り、バーチャル納骨堂といった新しい形も出てきています。
お墓の形は変わっても、「大切な人を思い、手を合わせる気持ち」があれば、それは立派な供養なのです。
■ 最後に
墓じまいは確かに手続きも気持ちも大変かもしれません。
でも、それは決して「ご先祖を粗末にすること」ではなく、「今の時代に合った供養の在り方を模索すること」でもあります。
昔のように大家族で生きていく時代から、今は一人ひとりが自分の人生を選び取る時代へと変わっています。お墓もまた、時代とともに変わっていくのは自然な流れなのかもしれません。
大切なのは、形ではなく、心。
どんな供養の形でも、「ありがとう」「会いたいな」という気持ちがあれば、それは十分にご先祖に届くのです。