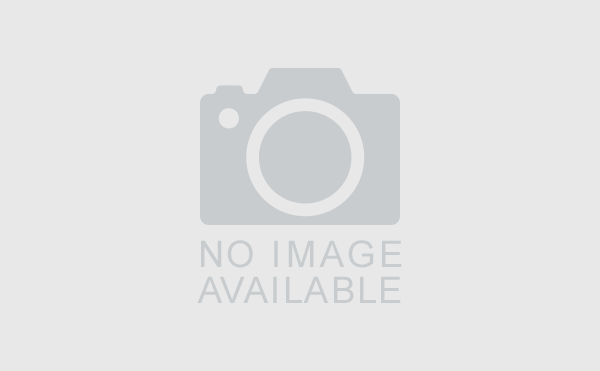墓じまいと件数と傾向
近年、日本全国で「墓じまい」と呼ばれるお墓の整理・撤去が増加しています。かつては家族代々が同じお墓を守り続けることが一般的でしたが、少子高齢化やライフスタイルの変化により、その風景は大きく変わりつつあります。
墓じまいの件数と傾向
近年の統計によれば、墓じまいの件数は年々増加傾向にあります。特に2010年代以降、都市部を中心に件数が急増し、地方でも同様の傾向が見られます。例えば、ある大手石材店のデータによると、2010年頃には年間数千件程度だった墓じまいの依頼が、2020年代には数万件にまで増加しています。
なぜ墓じまいが増えているのか?
- 少子高齢化と後継者不足
- 子どもが少なくなり、遠方に住む家族が増えたことで、お墓の維持が難しくなっています。遠隔地に住む子どもたちは、頻繁にお墓参りに行けず、管理が行き届かなくなるケースが増加しています。
- 都市化とライフスタイルの変化
- 都市部への人口集中により、地方のお墓が放置されがちです。また、核家族化が進み、「家族で守るお墓」という概念が薄れてきました。
- 経済的な理由
- お墓の維持費用(管理費や修繕費)が負担となる家庭も多いです。墓じまいをして永代供養墓や納骨堂に遺骨を移すことで、経済的な負担を軽減することができます。
墓じまいの流れ
墓じまいは単なるお墓の撤去ではなく、故人への敬意を込めた手続きが必要です。通常は以下のような流れで進められます。
- 家族・親族との相談
- まずは家族や親戚と十分に話し合い、みんなの意見を尊重することが大切です。
- 行政手続き
- 改葬許可申請書を役所に提出し、許可を得ます。
- 遺骨の取り出しと新たな供養先へ移送
- 専門業者と連携し、遺骨を丁寧に取り出し、新しい供養先に移します。
- お墓の撤去工事
- 石材店が墓石を撤去し、更地に戻します。
今後の展望
墓じまいの増加は、単なるトレンドではなく、社会構造の変化を反映しています。今後は、より多様な供養の形が求められるでしょう。樹木葬や海洋散骨、オンライン供養など、新しい供養文化が広がっています。
まとめ
墓じまいは、故人への想いや家族の絆を再確認する機会でもあります。大切なのは、形式にとらわれず、心から納得できる形で供養することです。今後も社会の変化に合わせて、柔軟な考え方が求められるでしょう。